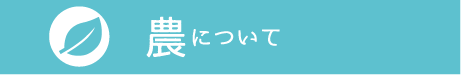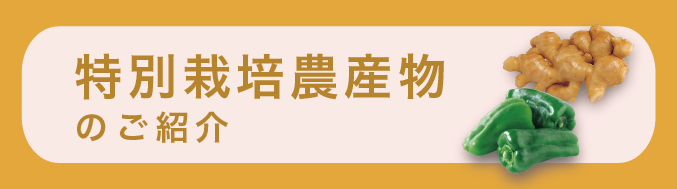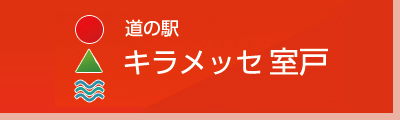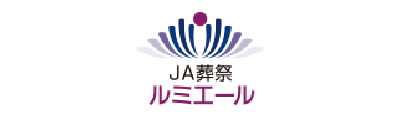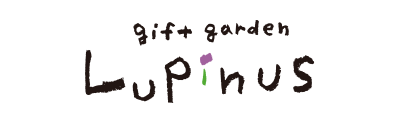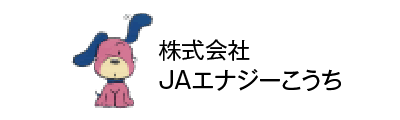JA高知県幡多地区で栽培されているブランドイチゴ「おおきみ」は、栽培労力の省力化を目指して開発された品種で、玉が大きく味と香りに優れている。都市圏の百貨店などで「高級イチゴ」として販売されているほか、シンガポールなど東南アジアにも輸出されている。「おおきみ」の栽培と今後の展望について取材した。
高い糖度と香り
糖度、香りが高い大玉イチゴ「おおきみ」は2008年、当時の「独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構九州沖縄農業研究センター」(現在は「国立研究開発法人」)で開発された品種。平均果重が20グラムと大きい上に形がそろいやすく、農薬散布の手間を抑えられるよう病気に強い品種として育成された。減農薬栽培に適し、安全・安心意識の高まりにも応えるイチゴだ。
「おおきみ」育種の背景には、イチゴ栽培の省力化がある。通常、イチゴの促成栽培は1玉当たりの価格が低いため、売り上げ確保のためには相当量の作付・栽培が必要となる。出荷時期になると、毎日の収穫作業に加え、選果してパックに詰める作業に膨大な時間を必要とする。
「おおきみ」は花数が通常のイチゴの3分の1と少なく摘果作業が要らず、収穫作業は2~3日に1度。その分、栽培管理に手を掛けられる。

都会の百貨店の他、東南アジアへも輸出される「おおきみ」
新品種への挑戦
幡多地区で「おおきみ」の栽培が始まったのは、12園芸年度のこと。生産者2人、作付面積約16アール、出荷量約1・8トンからスタートした。その後、徐々に拡大し、現在は8人が約67・4アールで栽培しており、出荷量は約12・2トンまで増えた。
最初に手掛けたのは、JA高知県中村支所おおきみ部会の部長を務める野口典久さん(65)。30年前に高知市からUターンして就農し、普通のイチゴを作っていたが、収穫のピーク時には夜遅くまでパック詰め作業を行い、翌日はまた早朝から収穫作業に追われ、夫婦2人では重労働だった。
ある時、視察で同センターを訪れ、「おおきみ」に出合った。大玉で農家にとっては都合の良い品種だが、収量が少ないため高付加価値商品として高値で販売しなければ経営が成り立たない。
生産者からは「そんな高いイチゴが売れるはずない」と敬遠されていたが、野口さんはこれをチャンスと捉えた。採算ベースに乗せるためにより大きく、美しく、おいしい栽培方法を確立し、「高級イチゴ」として販路を確保すればよいと考え、新品種へのチャレンジを決めた。

「県内に仲間を増やし生産を拡大したい」と話す野口典久さん(写真はいずれも宿毛市平田町)
「量より質」
試験栽培を始めると「色付きが悪い」「害虫に弱い」などの特性が明らかになった。今までのイチゴとは管理の仕方も異なり、結実しない年もあったという。
「栽培は手探りで、商品として出荷できるようになるまで3~4年かかりました」と野口さん。おいしそうな赤色にするために白いマルチシートを導入するなど、試行錯誤しながら最適な管理方法を編み出し、ブランド確立のために厳しい選果基準を設けた。
現在、8人の生産者はそれぞれ苗作りから手掛け、ミツバチを使って受粉。天敵昆虫を使って極力農薬を使用しない栽培方法を取っており、「エコファーマー」の認定を受けている。
「一番の問題は販路の開拓でした。付加価値の高い贈答用イチゴとして、東京・大阪の百貨店で販売することが決まりました。しかし、花芽分化が遅いので一番の需要期であるクリスマスやお歳暮に間に合いません。収穫は1~5月で、2月がピーク。その時に商品が動かないのは困るので、海外への輸出を考えました」と野口さんは言う。
「おおきみ」はその姿の美しさとおいしさから、価格は普通のイチゴに比べはるかに高い。39グラム以上の「5L」サイズなら9玉入りの化粧箱に詰められ、1箱7500円の「高級イチゴ」として都会の百貨店に並ぶ時もある。
一玉一玉、手作業で丁寧にピンクのキャップに包まれたへた付きの大きなイチゴは堂々たる風格が漂う。「量より質」を狙った差別化商品で、贈答用としての需要が高い。
台湾向けから始まった海外輸出も好調で、現在は香港、タイ、マカオ、シンガポール、マレーシアにも出荷し、現地の富裕層から高い支持を得ている。2月には生産者とJAが商談のためシンガポールを訪問。日本の果物は安全・安心の面で関心が高く寄せられ、好まれるのだという。

傷つけないよう細心の注意を払いながら、手作業で一玉一玉をキャップで包み箱詰めする
技術や情報共有
「おいしい」と誰もに喜ばれる「おおきみ」だが、日本で産地として栽培に取り組んでいる所は少なく、高知県は高いシェアを占めている。野口さんは「栽培方法の確立とブランド化、販路拡大に努めてきたその成果です」と話す。
生産者たちは日々、栽培の技術や知見を共有しながら切磋琢磨(せっさたくま)し、品質向上と生産力向上に力を入れている。
「みんなで頑張っていますが、需要に応えきれていません。今後もまだまだ需要は拡大するでしょう。県内で仲間を増やし、技術や情報を共有しながら高知県産『おおきみ』の生産を拡大していきたいです」と意気込んでいる。